令和7年度 視察概要
令和7年度 視察概要

1 視察日 8月4日、5日、6日
2 視察先 大阪府大阪市 大阪市工業用水道特定運営事業について
広島県広島市 広島駅南口広場の再整備等について
静岡県浜松市 公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業について
3 参加者 手塚泉、岩井潤子、茂木祐佳里、柴田賢司、保坂栄次、高橋英樹、馬上剛、塚田典功
4 視察結果
本委員会においては、「公共交通の結節機能とまちづくり」「ウォーターPPP」について、先進都市の事例を学び、本市の参考とするため、行政視察を行った。
建設常任委員会委員長 手塚 泉
1 大阪市工業用水道特定運営事業について(大阪府大阪市)
大阪市では、工業用水道事業において、中長期的な給水収益の減少や、埋設管路のうち約78%が法定耐用年数40年を超過するなどの施設面の老朽化に伴う更新需要の増大等の経営課題を抱えていた。
令和4年度からPFIを導入し、事業は運営権者である「みおつくし工業用水コンセッション株式会社」に移行。特定運営事業を開始して以降、新料金プランや新規利用者の負担軽減策の実施により収益性の向上を図るとともに、ICT、IoT技術を活用した管路の状態監視保全を導入することで、大規模漏水の抑制と更新投資の抑制を効果的に両立し、管路の長寿命化を図っている。
大阪市は地方公営企業の管理者として、工業用水を供給するための施設を所有し、運営権者が業務を確実に履行し市の要求水準を満たす業務品質であるかを確認するためのモニタリングを実施しており、このモニタリングは、本市においても民間参入を行う際に内容を精査すべき点である。
本事業により、運営権者の経常利益は約1.1~2.2億円の黒字と計画値を上回る実績であり、大阪市は主に資産管理を担い、経常収支は概ね収支均衡となっている。
大阪市の官民連携の取組は、公による制約を排し、経営の自由度を高め、民間発想を最大限に活かすことができる官民連携手法の先進モデルであり、本市のウォーターPPPを検討するうえで参考になる事例であった。
2 広島駅南口広場の再整備等について(広島県広島市)
広島市では、交通結節機能を有する広島駅南口において、広島電鉄の路面電車のラッシュ時の渋滞緩和や所要時間の短縮、バスからJR線への乗継利便性の向上などの課題に対し、平成31年度より広島駅南口広場の再整備事業に着手している。
令和7年8月3日には、広島電鉄がJR広島駅ビル2階に乗り入れる駅前大橋ルートが開業し、路面電車への乗り継ぎ利便性が向上したところであり、今後は、周辺ビルを繋ぐ歩行者デッキ、賑わい広場、バス・タクシー・マイカーエリアなどの整備が計画されるなど、県都の玄関口にふさわしい一体的な整備と乗り継ぎ利便性の向上が着実に進んでいる。本市でも課題となっているマイカーの滞留については、過度な流入を防ぐ取組が真価を発揮できるよう乗降スペースとのバランスの検討が重要である。
広島市が実施している市民を巻き込んだ様々な勉強会や社会実験の実施、その成果の共有など事業に対する市民理解を促進する取組は、今後の本市の事業推進において大変参考となるものであった。
3 公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業について(静岡県浜松市)
浜松市では、行財政改革の一環として組織のスリム化に取り組む中、平成17年の市町村合併に伴い編入された流域下水道が平成28年に静岡県から事業移管されたが、本処理区に従事する職員について大幅な増員は難しい状況であった。平成30年度には、これまで公共や民間等に散在していたヒト(維持管理)、モノ(投資)、カネ(財源)、情報などの経営資源を運営権者に集約し、経営・改築・維持管理と性能発注を請け負う部分型コンセッション方式を西遠浄化センター及び2か所のポンプ場に導入した。
事業者選定にあたっては、競争環境の確保や官民の情報格差の解消、頑張らないと損をする効率的運営への動機づけ等により、より良い提案を引き出すための工夫を行うことで、運営権対価25億円を確保するとともに、VFMは当初想定の7.6%から14.4%(86.6億円)まで拡大することができた。
浜松市の民間の自由な提案を受け入れた点、持ちうる情報を最大限オープンにした情報提供と応募者からの要望に応じ追加の対話等を重ねた点、運営権対価を0円以上とした点などは複数の事業者が参加しやすく、競争原理を働かせた有効な取組である。
浜松市の取組は、下水道事業における将来的な経営課題に対し、市民サービスを低下させずに行政のスリム化を図ることで、技術の伝承や事業コストの縮減を実現させ、持続可能な事業経営に資する先進事例であった。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課
電話番号:028-632-2608 ファクス:028-632-2613
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

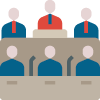
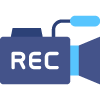
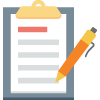
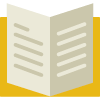

 市議会とは
市議会とは 議員紹介
議員紹介 議会改革・活性化
議会改革・活性化 会議の案内
会議の案内 会議の結果
会議の結果 請願・陳情
請願・陳情 議会広報
議会広報 情報公開
情報公開 議会事務局から
議会事務局から