3. どのような計画なの?
(1) 計画の概要
3つの基本目標を設定しています
すべての人々が「健康」で充実した人生を送ることができる「健康で幸せなまちづくり」を実現するため、次の3つの目標を設定しています。
- 健康寿命の延伸 健康で生きがいを持ち、自立して暮らすことができる期間を延ばす。
- 生活の質の向上 個人の価値観や心身の状態に応じて生きがいや満足感の持てるよりよい人生を送ることができるよう、生活の質を高める。
- 壮年期死亡の減少 働きざかりの人の死亡を減少させる。
9つの重点分野を設定しています
計画の基本目標を達成するため、健康寿命を短縮したり、壮年期死亡の原因となる生活習慣病とその発症などを予防することが期待できる生活習慣に関する9領域を重点分野として設定しています。
- 健康づくりの三大要素
(1)栄養・食生活、(2)身体活動・運動、(3)休養・こころの健康 - 生活習慣病の危険因子
(4)歯の健康、(5)たばこ、(6)アルコール - 生活習慣病
(7)循環器病、(8)糖尿病、(9)がん
6つのライフステージ区分を設定しています
健康づくりは、生涯を通して行うことが重要ですが、人生の各年代ごとに異なった課題があります。そこで、この計画では、ライフステージを生活習慣や身体的・精神的な発達状況、身体機能などに応じて6つに区分し、各ライフステージに応じた健康づくりの目標(健康目標)を掲げます。
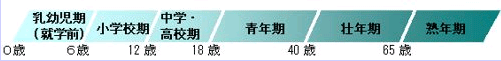
(1)乳幼児期(就学前)、(2)小学校期、(3)中学・高校期、(4)青年期(18歳~39歳)、(5)壮年期(40歳~64歳)、(6)熟年期(65歳以上)
評価目標・目標値を設定しています
この計画は、市民や地域、行政、学校、職場などが共通意識を持って、一体的に健康づくり活動に取り組み、その成果を適切に評価して、その後の健康づくり活動に反映できるようにするため、「健康目標」を設定し、計画の目標年度である2010年までに目指す姿を示しています。
重点9分野の健康目標
- 栄養・食生活
栄養のバランスのよい食事を3食規則正しく食べる食習慣を身につけます。 - 身体活動・運動
日常生活の中で、自分に合った運動を気軽に楽しみながら継続して実践します。 - 休養・こころの健康
休養を積極的に取り入れ、ストレスを上手にコントロールします。 - 歯の健康
むし歯や歯周病を予防し、60歳で24本、80歳で20本の健康な自分の歯を保ちます。 - たばこ
未成年者の喫煙をなくすとともに、禁煙・分煙を積極的に行います。 - アルコール
未成年者の飲酒をなくすとともに、節度ある適度な飲酒を実践します。 - 循環器病
生活習慣の改善に努め、肥満を予防し、循環器病の発症予防に努めます。
40歳になったら、年に1回必ず健康診査を受診し、早期発見・早期治療に努めます。 - 糖尿病
40歳になったら、年に1回健康診査を受けます。糖尿病にならないように日頃から太りすぎに注意します。 - がん
女性は30歳、男性は40歳になったら、年に1回がん検診を受け、自分自身の健康を見直します。
目標値
目標値の例=2010年(平成22年)の目標値
- 栄養・食生活
朝食を欠食する人の割合(小・中・高校生):0%にする。 - 身体活動・運動
息が少し弾む程度(30分以上継続)の運動を週2回以上する人の割合:増やす。 - 休養・こころの健康
睡眠による休養がとれていない成人(「いつもとれていない」「とれていないときがしばしばある」)の割合:40.2%以下にする。 - 歯の健康
むし歯のない幼児(3歳児)の割合:80.0%以上にする。 - たばこ
高校生の喫煙者(月1回以上)の割合:0%にする。 - アルコール
飲酒経験のある中学・高校生の割合:0%にする。 - 循環器病
基本健康診査の受診率: 55.0%以上にする。 - 糖尿病
基本健康診査で要医療に該当する人の割合:減らす。 - がん
がん検診受診者数:現状より5割程度以上増やす(胃がん・大腸がんは2.5倍、3倍以上増やす)。
目標値一覧
-
栄養・食生活 (PDF 336.3KB)

-
身体活動・運動、休養・こころの健康 (PDF 305.4KB)

-
歯の健康 (PDF 245.2KB)

-
たばこ、アルコール (PDF 261.8KB)

-
循環器病 (PDF 242.0KB)

-
糖尿病、がん (PDF 272.3KB)

計画の期間は?
- 平成14年度(2002年度)を初年度とし、平成22年(2010年度)を目標年度とする9カ年計画です。
- 目標年次の中間である平成17年度(2005年度)に中間評価を行い、計画の見直しを行います。
計画書等
計画書
-
全体概要 (PDF 56.7KB)

-
総論 (PDF 207.3KB)

-
各論(重点9分野その1) (PDF 277.6KB)

-
各論(重点9分野その2) (PDF 294.4KB)

-
各論(重点9分野その3) (PDF 146.9KB)

-
各論(ライフステージ) (PDF 121.5KB)

-
各論(推進体制) (PDF 32.2KB)

-
資料編(その1) (PDF 2.6MB)

計画書概要版
リーフレット
(2) 策定の過程
平成13年度
- 5月:庁内検討組織を設置し、検討を開始
- 7月から10月:市民健康意識等調査の実施
- 11・12月:関係団体との意見交換会の実施
- 7・12月:学識経験者、各種団体代表、公募委員等からの意見聴取
平成14年度
- 5・7・8月:学識経験者、各種団体代表、公募委員等からの意見聴取
- 9月:計画の策定・公表
- 10月から:市民および関係団体・機関への周知、計画の推進
「(仮称)健康うつのみや21プラン」策定に係る関係団体との意見交換会での主な意見
第1回ヒアリング 平成13年11月8日(木曜日)・12日(月曜日)
- 子どもの頃からの正しい生活習慣・意識啓発が重要。
- 嗜好とのバランスで市民の健康を考えることが不可欠。
- 気軽に手近なところでできる健康づくりを。
- 40~50代の男性への取り組みに重点をおくべき。
- 「地域」の役割が重要。
- まずは本人が自覚を持つこと、さらには周囲の支援が必要。
- ふれあいと交流の中で、身近なところでの健康づくりを。
- 家庭環境(生活リズムや余裕など)が子どもの生活習慣に影響する。
- 親や経営者といった人々が子どもの教育に与える影響に目を向けるべき。
- 自然とのふれあいの中で、親子のコミュニケーションや遊びを。主に、これから親になる世代、小中学生をターゲットに。
- 地域ぐるみのモラルづくりが重要。
- 「うつのみやらしさ」を重視すべき。意見交換会を開くだけではなく、それを実行に移せる計画づくりを。
第2回ヒアリング 平成13年12月18日(火曜日)・19日(水曜日)
- 健康づくりの行事やイベントに取り組む際には、親子で一緒にできたり、毎年継続して取り組むことができる等の「しかけ」が必要である。
- 子どもについては、身体面と並んで、精神面の健康が大きな課題である。
- 健康づくりには、幼児・小学生~中学生頃までの教育が最も重要である。
- 子どもの飲酒や喫煙には「家庭での親の言動」が強く影響している。
- 今の学校教育・学校保健では、薬物乱用防止と異なり「飲酒・喫煙」に関する取り組みに、そう力が入っているわけではない。
- 健康づくりを進めていくには、研修や運動する場・器具の使用等、「学校」と「地域」の連携をより深めていく必要がある。
- 飲料や食品の栄養成分については、市民に誤解されている部分がある。それを正しくを理解してもらうには、具体的な分かりやすい数字で示すことが必要である。
- 健康の保持・増進のためには、市民みんなが様々な形で、スポーツや運動に取り組む機会を設けていくことが重要である。
- 幼児・小学校・中学校期で、子どもが「きちんとした生活習慣」を身につけるためには、まず、親の自覚が求められる。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
宇都宮市保健所 健康増進課 企画グループ
電話番号:028-626-1128 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。














